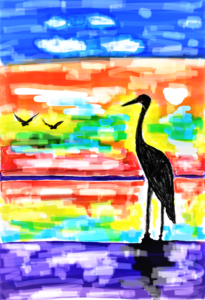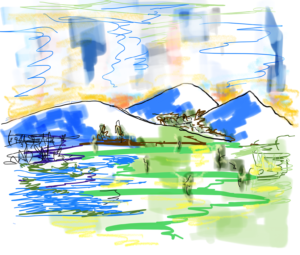ウチからの身近な観光地は、
北上すると丹沢の東あたり。
南下すると茅ヶ崎の海岸というところか。
どちらにしようかと思案するも、
やはり紅葉がみたいということで、
宮ヶ瀬湖に出かけてみた。
ここは例年、夏にバーベキューで来ていたが、
コロナ禍で今年は2回中止となった。
平日の午後だし
誰もいないんじゃないかと思っていたが、
そんなことはない。
結構の人出だった。
クルマは横浜・湘南・品川のナンバープレートが目についた。
小春日和だったが、ここはやはり寒い。
風も強い。
推定だが、東京や横浜よりまず5℃は低いと思う。
丹沢山塊の中腹だし、冷えるのはしょうがない。


視界がとても広いのがいい。
気が休まる。
夏の陽射しと較べると、
夕方とはいえかなり差し込む角度が低い。
陽射しがオレンジ色に映る。
みんな寝転んだり佇んでいたりと、
とってもゆったりとしているようにみえる。
(日頃は結構ハードで疲れているんだろうなぁ)
景色をみながら、
この一年があっという間に過ぎてしまったことに気づく。
みんなどうしているんだろうとかと、
久しぶりに改めて考えた。
いまのこの世の中、
何かがおかしい何かが変なのだけれど、
その正解が分からないでいる。
外界とのコミュニケーションが減ったことだけは、
確かなことだ。
「時代なんかパッと変わる」というコピーを思い出す。
確か、80年代のサントリーウィスキーのコピーだ。
ホントに時代がパッと変わってしまった。
このコピーの作者は、予言者か?
いや哲学者かも知れない。
優れたコピーって、商品や時代を飛び越えて、
スタンダードな一行として後世に残ることがある。
そんな一行をつくりたくて、この業界に入ったんだけどなぁ。
とにかく、この景色のお陰で、
普段は考えないいろいろなことに目が向けることができた。
貴重な時間だった。