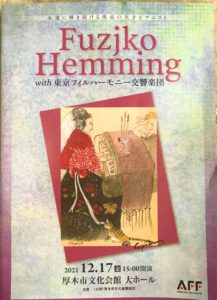ご存じ、キャロルのメガヒット曲。
我が青春の一曲でもある。
イントロからリードギターの高音でいきなり盛り上がる。
10代のボクには斬新かつインパクトがありました。
すげぇーと思いましたね。
で、メンバーの革ジャンとリーゼントがカッコよかった。
その頃、ボクたちの先輩はアイビーと呼ばれる格好が多かった。
流行の震源地は、VANジャケット。
紺のブレザーにコットンパンツをはいて、
レジメンタルのネクタイを締めたりしていた。
女性もトラッド・ファッション全盛。
横浜・元町の店フクゾウが爆発的人気となり、
「ハマトラ」と呼ばれる格好が流行った。
いずれきれい系。
が、キャロルはおとな社会への反逆まるだしの歌と格好でデビュー。
10代はみんなそこにハマった。
よって当時すでにハタチを超えたお兄さんお姉さんたちからは、
あまり人気がなかったのかもね。
ボクは10代のストライクゾーンだったので、
もろに影響を受けてしまいました。
余談だけれど、フーテンと呼ばれるひともよくみかけた。
この方たちは、いつでもどこでも道に座り込んだりして、
片手に酒の瓶とシンナーとビニール袋をもっていた。
当時、街にははこういうひとがパラパラいました。
ボクの先輩にひとりこの手の方がいましたが、
不慮の事故で亡くなってしまいました。
いま思えば、妙な最後でした(具体的には書きませんが)
で、クルマの免許取りたて、青春真っ只中のボクとしては、
即キャロルのレコードを買い、それをテープに録音して、
走りながらカーステレオで繰り返し繰り返し聴いていた。
演歌やフォーク、歌謡曲全盛の時代に突然あらわれた、
日本初ではないけれど、
メイド・イン・ジャパンのロックンロールバンドだった。
それまで洋楽でロックンロールはよく聴いていたけれど、
日本発というのはかなり珍しいということで、
「ファンキーモンキーベイビー」はいきなりヒットチャートを駆け上がった。
この歌が流行ってから、
なんだか遊んでいる10代の皆さんを取り巻く空気が一変した。
定番のクルマ・バイクに女の子―
そこにサイコーの音が加わったからだ。
海の向こうでは延々とベトナム戦争がつづき、
ある日突然オイルショックなるものが起き、
朝起きると「危機」が叫ばれ、世の中は混乱し、
ボクはトイレットペーパーを買ってこいと母に怒鳴られた。
街ではマツダのロータリークーペが疾走し、
中島みゆきが「時代」を歌い、
ユーミンが「あの日にかえりたい」でメジャーになり、
遊び仲間が事故やシンナーで何人か死んでしまい、
ボクは将来が全く見通せないでいた。
ファンキー・モンキー・ベイビーの歌詞の意味は、
当時からよく分からなかったし、考えもしなかった。
ただ、♪いかれてるよ♪の歌詞に象徴されるように、
なんだか理屈ではないエネルギーのようなものを、
みんなが受け取ったのだろう。
で、なんだかみんなイカれてきた、ような気がしたのだ。
イカれてもいいんじゃない?ともきこえたからだ。
うっくつした時代の空気を蹴散らすエネルギーに
後押しされたボクたちは、
自分の未来を真剣に想像することもやめてしまった。
そんな一瞬でもあった。
そしてイージーに過ごす時間、酔っているような毎日は、
あっという間に過ぎていった。
あの陶酔していたような時間はいったい何だったのか?
それは思い返しても、いまだ、その輪郭が描けない。
で、ボクくらいの年代になるとだけど、好きなアーティストや楽曲も、
だいたい100や200はあると思う。
ながい時間にいろいろな歌も聴いてきた。
ジャズやボサノバやポップス、そして民族音楽、
たまにクラシックにも手をだしたこともある。
なのに不思議なことに、いまでもキャロルは特別なのだ。
そこには理屈では語れないなにか、
が相かわらずボクの記憶のなかに横たわっている。
聴いていた自身の幼さと、そのころのこころの有りよう、
そしてそこに流れていた時代の空気…
いろいろなものが凝縮された心象風景が、
人生の道連れとしてあとをついてくるのだろうか。