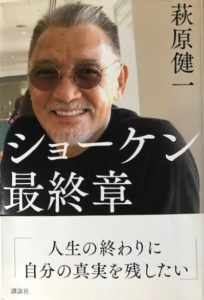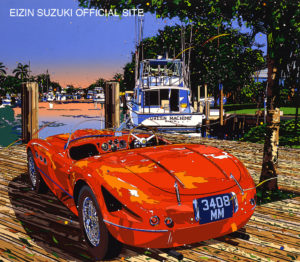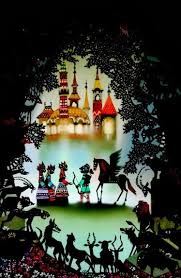東京・竹芝さん橋で、新・さくら丸に
親友の丸山と乗船した。
ふたりとも、船旅は初めてだ。
船は、本州に沿って航行を続けるという。
360度、どこを見ても海というのは、
とても新鮮な体験だった。
が、伊豆大島を過ぎ、三河湾あたりで
そろそろ海の景色にも飽きてきた。
デッキで潮風にあたりながら、
ずっとビールをラッパ飲みしていたので、
少し吐き気を催してきたみたいだ。
初めての船酔い。
ボクと丸山は船室に戻って、ベッドに横になった。
そこで、ボクは吐き気を抑えながら、
必死で何かを考えようとしていた。
丸山もきっとそうだったと思う。
(この先、ボクはどこへ行こうとしているんだろう?
いったい、ボクは何をめざしているのだろう?)
その問いは、この船旅ではなく、
自分のこれからの身の振り方だった。
この頃、ボクたちは自身でもイラつくほどに、
自分のことが分からなくなっていた。
そして日々、迷ってばかりいたのだ。
ボクは、大学の付属校へ通っていたにもかかわらず、
カメラマンになるのが夢だったので、
大学への進学は2年の秋ごろから辞退していた。
が、その意思を学校へ提出した後で分かったことなのだが、
カメラマンになるには、それなりの高い学費と、
高額なカメラ機材を買う費用、
そして自宅に現像室を設置しなくてはならなかった。
何をやるにも事前の準備不足が、
ボクの欠点だった。
そのことを一応両親に話してはみたが、
予想どおりの回答が返ってきた。
父は母にこう話したそうだ。
「あんな極道息子に出す金はない」
この文句は、ボクも予想していた。
当然といえば当然の報いとも言える。
なにしろ、高校時代のボクに、
褒められたところは、ひとつもないのだから。
一年で吹奏楽の部活をやめてしまったボクは、
地元の友達といつも街をふらふらとしていたし、
そうした仲間と酒を飲み、タバコをふかし、
ディスコで朝まで踊ったりしていたのだ。
一応、なんとか高校は卒業したものの、
まともな就職もあきらめて、
いろいろなバイトで生計を立てていたが、
空虚な毎日で、行き場をなくしていた。
一方、中学で同級生だった丸山も、
家の事情で普通高校をあきらめ、
自衛隊の少年工科学校の寄宿舎へ入ったものの、
キツい学業と訓練に明け暮れた毎日に嫌気が差し、
バイク事故でケガをして入院したことも重なり、
学校を中退し、疲れ果てていた。
やはりボクと同様、鬱屈した毎日を送っていた。
ヒマで退屈なあの夏。
ボクは、永遠にどこまでも、
何の目的も希望もない毎日が続くのではないか、
という恐怖に幾度も襲われた。
その夏は、とにかく24時間がとても長く、
朝も昼も夜もつねに憂鬱だった。
汗が止めどなく流れる、とても暑い夏。
ボクは丸山のアパートで過ごす日が多くなった。
しかし、お互いに何もすることがなかった。
そんな日が幾日も続いた。
ふたりはあたりが暗くなると、
だるい身体を引きづるように、
連れだって近所の居酒屋へでかけた。
そこで安いアルコールを飲み、
酔いがまわってくると、
ふたりは真剣な顔つきになってしまうのだ。
「俺たちは一体なにものなのか、
この先、何がしたいのか?」
そんな全く結論の出ない議論のようなものを、
延々としていたのだ。
当然、出口のようなものはみつからない。
それは、まるで明日へと繋がる時間が、
完全に閉ざされたような失望感を伴っていた。
そんなやるせない毎日が続いた。
相変わらず強い陽が照りつける或る日の夕方、
ボクと丸山はいつものように、
近所の商店街をだらだらと歩いていた。
と、新しいビルの一階に、
オープンしたばかりの旅行代理店が目に入った。
通りから眺めるガラスのウィンドウには、
北海道3泊○万○千円~とかアメリカ横断7日○○万~とか
いろいろな手書きの紙がペタペタと貼ってある。
そのチラシのような張り紙を、
ふたりでぼおっーと眺めていた。
何の興味も湧かないのだが、
ふたりはなにしろ暇なので、
その張り紙を隅から読み始めた。
が、時間がどのくらいか経過した頃、
ボクのアタマに何かがひらめいたのだ。
丸山をのぞくと、
彼の横顔にも同様の表情が見て取れた。
ふたりは、その小さな店舗のガラス扉を開け、
相手の説明もたいして聞かないまま、
沖縄行きの予約をした。
店を出ると、陽はとっくに暮れていた。
相変わらず熱気が身体にまとわりついて、
また汗が噴き出す。
ボクらは商店街を再び歩き出すのだが、
それは自分たちでも驚くほど軽快な足取りだった。
その日を境に、ボクたちの気持ちに、
ある変化が生じていた。
(続く)