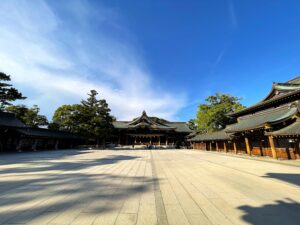仕事柄、ビジネスホテルをよく利用する。
最近は、安かろ悪かろのホテルが目に付く。
築古で極めて狭い部屋が増えた。
コストダウンで洗面道具、特にヒゲ剃りなど
フツーにないところもある。
インバウンド需要で宿泊費も高騰しているし、
こっちは踏んだり蹴ったりなのだ。
あるとき楽天トラベルで、
山の手線沿いのビジネスホテルを探す。
某駅前のビジネスホテルが目に留まる。
サムネ写真を凝視しホテルの外観をチェック。
入り口も豪華で石の素材など使ってある。
この外観なら、部屋もそう酷くなさそう、
という判断から予約を入れた。
当日、そのホテルは確かに駅前にあって、
便利じゃんとうれしくなる。
入り口が写真のとおりかっこいい。
なかに入るとフロントが豪勢なつくりで、
ライティングにも凝っている。
雰囲気いい。
他のチェックイン客とバッティングしたが、
日本人とおぼしき人は私以外誰もいない。
韓国、中国、インドネシア他、
アジア系に混じって欧米系も目に付く。
(皆、ここの便利さと豪華さに惹かれのかな)
フロントの女性は、皆日本人ではない。
が、言葉は通じるのでOK!
でですね、
キーをもらって長い廊下を歩いていると、
途中から建物の雰囲気が変化してきた。
床のリノリウムが古く、めくれが目立ってきた。
廊下の壁紙もかなりくすんでいる。
窓枠をみると、サッシに白錆が浮いている。
と、急に段差があり、
あきらかに隣の建物に入ったと感じた。
私の部屋はフロントから一番遠くにあり、
そこは、このホテルの外観、入り口とフロントの豪華さとは、
全く違う様相を施していた。
扉は、かなり使い込まれていて、
塗装の剥げや錆も目に付く。
推定するに、築後50年以上は経過している。
(大きな地震がきたら死ぬな)
で、部屋に入ると、すえたにおいがするので、
内部を見渡すと、風通しや日当たりが全くない。
カビのにおいだろうと推測する。
部屋は全体に古びていて、
酷く狭いL字型で、Lの出っ張ったところに
バスルーム兼トイレ兼洗面台が詰め込まれている。
とても使いづらいのは一目で分かる。
というのも、ボクはこの手の部屋には、
幾度となく引っかかっている。
懲りないのがボクの欠点なのは承知しているが、
まぁ予算も限られているし、よってこの手の部屋には
時々だけど当たってしまう。
そこでボクはあるときから、
このような酷い部屋で
如何に快適に過ごすかという課題に、
取り組むことに切り替えた。
当初は、空気の入れ換えもできない
窓が壊れた部屋に通されて憤慨し、
フロントにクレームを入れて、
部屋を換えさせたりもした。
が、いい加減な部屋選びをするおのれに
腹が立つようになり、自己責任だろうと
自分に厳しく対峙することに決めた。
以前、山中湖にてキャンピングカーで
寝泊まりしたとき、最初はその狭い車内で、
飯の支度をしたり、それを片付けないと
ベッドがセットできなかったりと、
結構マメにやらないとキャンパーになれないと
実感したことがある。
思えばハズレのビジネスホテルも同様で、
極小空間で過ごすには、アタマの切り替えと
智恵がいるものなのだ。
で、どうアタマを切り替えるのかだが、
たとえばそれを逃げられない運命として捉える。
(なんだか話がおおげさになってきた)
よって、そのなかでなんとかしなくては
生きていけないよとおのれに教え込む。
(それは嘘だと深層心理は知っているが)
そもそも私は閉所恐怖症なので、
このあたりの課題はかなりハードルが高かった。
(自分がつくった壁は自分で壊せ!)
なのに、楽しくなければビジネスホテルじゃないと、
おのれを洗脳し、ホテルの環境の悪さなど
取るに足らないものなのだと、思うようになってきた。
(なんだか怪しいテレビ局のコピーと被る)
こうして、アタマを切り替え、鼻歌を歌いながら、
細かな工夫を繰り返し、
いまでは快適なビジネスホテルライフを
満喫している。
↑〆が嘘くさいですね!