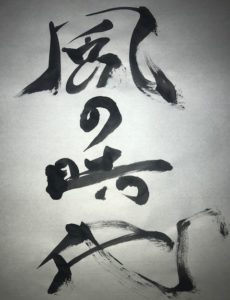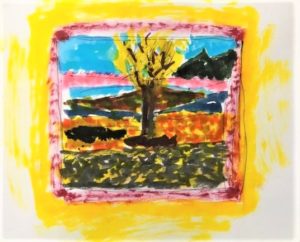70年代の中頃だったか、
僕は沖仲仕という仕事をしたことがある。
沖仲仕とは、港湾労働者のこと。
港で荷役をする肉体労働者だ。
いまは、荷物はだいたいコンテナなので、
大型クレーンでそれを吊り上げれば、
事足りる。
僕の若いころは、
それを人力でやっていたのだ。
岸壁に直接接岸できない大型の船だと、
荷を受け取って港におろすため、
小さな船が間に入らなければならない。
その荷物をひとつひとつ人力で
作業するのが、沖仲仕だ。
陸と海の間を取り持つ仕事なので、
沖仲仕。
船に揺られながら、一日中荷役をする。
波の荒い日は、吐く人間も出る。
真夏の暑い日などは、昼飯ものどを通らない。
僕がなぜそんな仕事にしたのかだが、
趣味のクルマに入れ込んでしまい、
借金がかさんだのと、
あとは遊びすぎてしまい、
それらの返済に追い詰められていたからだ。
当時のバイトの相場は、
一日3000円くらいだった。
普通のバイトでは、全く返済に追いつかないと
悟った僕は、突飛なバイトばかり探していた。
当時はベトナム戦争が激しかったので、
金に困っているある知り合いは、
戦死した米兵の死体洗いを真剣に考えていた。
そのバイトの噂は、
若い僕らの間を駆け巡ったが、
では一体どこへ行けば
そのバイトをさせてくれるのか、
まず入口のようなものが、
結局誰も分からなかった。
バイトは、日当3万円~5万円くらいだったと
聞いた。
あれは都市伝説だったのか、
それはいまでも分からない。
バイトの内容はこうだ。
プールのようなところに死体が
いくつか浮いているので、
一体ごとに回収して、
身体じゅうの穴という穴に脱脂綿を詰め込み、
死体をきれいに拭いて、棺におさめる。
そのような内容だった。
僕は臆病なので、
そうした恐ろしいことには
とても耐えられない。
次にバイト代が良かったのが、
一日1万円もらえる沖仲仕だった。
この仕事も、ひとから聞いた話からだった。
まず、朝の7時だったか8時だったかに、
横浜の仲木戸駅の付近をプラプラする。
それも何かを探しているように。
すると、手配師と呼ばれる
人集めがやってきて声をかけてくる。
そこで仕事の概要とギャラを提示する。
合意すると、紙っきれの簡単な文面の下に
朱肉で親指の拇印を着く。
そして10人くらい集まると
マイクロバスに揺られて、
岸壁に着く。
で、小型の船に乗り込む次第。
そんな仕事にやってくる人間は、
やはりと言うべきか、
皆一様に訳ありというか、
一癖も二癖もありそうというか、
外見からしてフツーな感じがしない。
これは後に気づいたのだが、
どのひとも家のないのは当たり前で、
木賃宿でその日暮らしが多かった。
公園とかで寝ているひともいた。
が、お互いにどんな人間なのかなんて、
誰も話したり触れたりしない。
酒焼けと日焼けが混じって、
どの顔もどす黒くて、
やたらとシワが深い。
歯が抜けているひとも、
かなりいた。
仕事は殺伐としていた。
すぐケンカが始まる。
それがひんぱんだった。
あるとき
血だらけのふたりが殴り合っていた。
現場監督がそれを見つけると、
平然とヘルメットでふたりを殴って、
そのケンカはおさまった。
それが日常茶飯事。
普段の風景なのだ。
あるとき、頭上数十メートルから、
クレーンに積んだ荷が船に落ちてきた。
僕のすぐそば、
50センチから1メートル近くで、
ドスンとすごい音がした。
当たっていたら確実に死んでいた。
驚いてまわりを見渡すと、
誰も顔色ひとつ変えない。
恐ろしい仕事だと思った。
この激しい労働の後は、
心身ともにズタズタになる。
どうしてもまともではいられない。
酒場、キャバレーと渡り歩く。
でグダグダに酔って、
やっと正気に戻れる。
そうでもしなければやってられない。
そんな仕事だった。
極度の疲労とストレスと恐怖。
それを紛らわすのに
すべて使い果たしてしまう。
そんな仕事は数週間でやめた。
金が貯まらないどころか、
命があやうい。
借金なんか減る訳もない。
明日のことも考えられない。
夢も希望もない。
ただ心身の疲労だけが、
いつまでも残っていた。
が、ふと思ったのは、
僕にはやめることのできる選択肢があった。
他で新たなバイトを探せば、
なんとかなる。
では、あのひとたちはどうだろう?
あの仕事の毎日は、残酷過ぎる。
考える余裕も体力の回復もないまま、
日々が過ぎていってしまうのではないか。
その先はみえている。
それを思うと、極度に憂鬱になった。
このバイトでの経験は、
僕にいろいろなことを教えてくれた。
それは経済的なことだけでなく、
これからどう生きていくか、
ということも含めて。
それからしばらく、
僕は時給の安いコーヒーショップで働いた。
それはとても穏やかな日々だった。