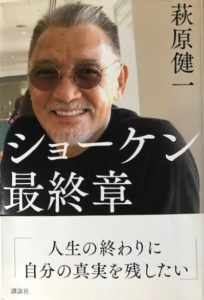その1 フリーへの道
きっかけはいろいろあるだろうけれど、
最近はフリーになる人が多いと聞いた。
社会構造の変化とか働き方の多様性とか、
そうしたものがフリーへ向かわせるのかも知れない。
ムカシはフリーへの敷居が高かった、というと語弊がある。
正社員でいたほうがいろいろといい時代だったから、
フリーになる必要性があまりなかった。
そもそもフリーの土壌がまだできていなかった。
敷居が高いというよりフリーの需要がなかったとしたほうが
正確な表現かも知れない。
しかし、働き方に関してなにか思うところがある、
独自の労働哲学をもっている。
特別のスキルをもっていて独りで稼ぐ自信がある。
こうした人たちは早々とフリーで働いていた。
さて、一念発起してフリーになる人がいる。
なんとなく成り行きでフリーになった人もいる。
資金等、準備万端でなる人。
あらかじめクライアントを確保してから、
という運のいい人もいる。
私的なことだが、
私の場合はスタートは成り行だった。
当時、勤めていた広告会社の経営が傾き、
ひとりふたりと会社を去るひとが出てきた。
「うーん困ったなぁ。子供もいるし、
家賃も払わにゃならんし…」
そんなのんきなことを思いながら数ヶ月が過ぎたころ、
いきなり会社の全体会議が開かれ、
そこで社長が「会社の危機的状況」を初めて直に口にした。
彼は涙を浮かべていた。
いきなり焦った。
不安が現実のものとなった。
身の振り方を考えねばと、
とりあえず家には真っ直ぐに帰らず、
会社の近くにある地下のバーでビールを飲みながら、
今後のプランを考えることにした。
家に直行すると奥さんにバレる、
そして子供たちの屈託のない笑顔なんかみたら、
泣きそうと思ったからだ。
地下のバーに出入りしていることを
会社の仲間に話すと、次第に未来の落ちこぼれが
集まった。
誰かが、いやこの私だったのかもしれない。
よく覚えていないが、
「この際、ここにいる俺たちで会社つくっちゃおうか?」
となった。
いい加減な提案だったが、なんだか希望の光がみえてきた。
それはみんなも同じだった。
「会社っていったいどうやってつくるんだ?」
「そこからだな。まずスタートに立とう」
「なんとかなる」
「なんとかなるかねぇ…」
そんなこんなで、約3ヶ月後に、
私たちは青山一丁目にあるきったないビルの一室を借り、
登記を済ませ、会社をオープンした。
そして倒産しかけている私たちの会社の社長と数回話し合いをもち、
クライアントを引き継ぐ、という形でスタートを切ることができた。
交換条件としてそれまでの給料の未払いなどは不問とすることとした。
これは、恵まれた独立の一例といえるだろう。
職場となった青山一丁目のそのきったないビルの一室は、
ときたま馬鹿でかい気味の悪いネズミが走っていたのを
何度かみかけた。
以上の私の例は、フリーというより会社設立の話だが、
ホントのフリーの話は次回にする。
後に、私はここを辞めてホントのフリーとなったのだが、
それはフリーの種類からいえば発作的フリーというもの。
これは、間違いなく例外なく茨の道が待っているので、
まずおすすめはしないフリーだ。
これはのちほど書くとして、
フリーって「Free」なのだから、直訳すれば自由のはずだ。
フリーになるとホントに自由になれるのか?
フリーという自由な働き方とは?
そのあたりもおいおい書く。
で話を元に戻す。
フリーは誰でもすぐになることができる。
免許も資格も何もいらない。
ただフリー宣言すればいい。
それだけのことなのだが…
(つづく)
次回は
・発作的にフリーになった惨めな話
・フリーになるとホントに自由になれるのか?
・フリーという自由な働き方とは?
などを予定しています。