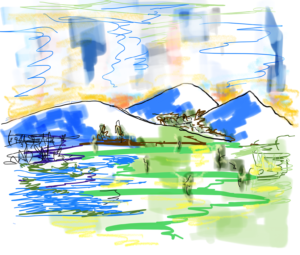花束って、
もらうととてもうれしい
あげてもやはりうれしい
そこにはきもちっていう
不思議なものを伝える
電気とか空気振動にも似た
見えない伝達機能のようなものが存在していて
ちょっとした感動がうまれたりする
赤いバラの花、カーネーション、真っ白なユリのはな
黄色いスィートピー、すがすがしいキキョウの紫
そしてカスミソウ、麦の穂やら
いろいろな花でにぎわって
いろいろな色が交りあって
想いが込められて
花束はあたらしい生命に生まれ変わる
とても幸せないっしゅんは
きもちを伝える方も
受けとる側も
花の命はみじかいけれど
とてもしあわせな命