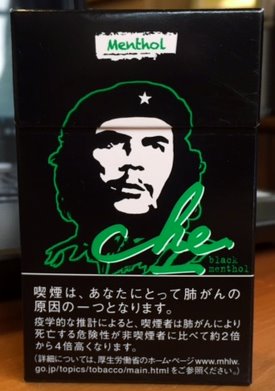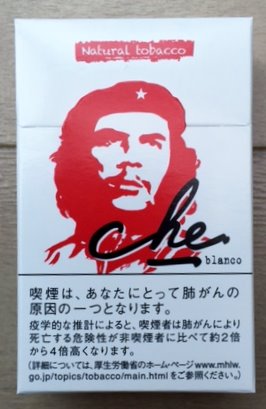元町の端、元町プラザビルのなかにある老舗レストラン、
「フィシャーマンズワーフ」は、安くてうまい。
ここでメシを食って通りをぷらぷら歩いていると、
バッグの「キタムラ」、パン屋の「ポンパドール」、
トラッドファッションの「フクゾー」と、
次々に懐かしい店が顔を出す。
この街も年輩の方が圧倒的に多い。
それも一見、生活にゆとりのありそうな方ばかり。
ケータイで話している高年紳士の会話が
すれ違いざまに聞こえてしまった。
「私はあの例のビルを買おうと思っているんですよ」
「…」
私たち夫婦は無言で歩き、程なくして「いまの会話聞いた?」
「うん、ビックリした!」
この街は、学生時代からちょっと敷居が高いとは思っていたが、
それはいまも変わらないんだなぁ。
先ほどの会話がそれを象徴している。
元町商店街の裏通りに入ると、このあたりも店が増え、
表とは異なった個性的な雰囲気を醸し出している。
おっと、空き地に真っ白のロールスロイスが鎮座する。
ここは、ベンツなんかより小洒落たミニクーパーなんかも多い。
なんだか居心地が悪くなってきたので、元町散歩中止。
「中華街に行こう」
元町を外れ、川を渡ると
中華街の南に位置する朱雀門に出る。
元町とは打って変わって人通りが多く、
うるさいというか賑やかというか、
ちょっとほっとするが、
あの中華街独特の色使いは強烈で、
もうなんだか、街全体が赤い絵の具をまき散らしたようだ。
目がチカチカする。
朱雀門近くにあるパワーストーンの原石が置いてある店をチェックし、
ヒマラヤ水晶が気になるも、また買いに来ようと出直しを決める。
で、数年ぶりに歩いて気になったのは、占いの店が更に増え、
おおげさに言えばだが、ここ中華街が占いの街と化していたことだった。
どの店も、若い子が列をなしている。
(どこかのテレビとか雑誌にでも取り上げられたのかな?)
一時は、肉まんブームみたいのがあり、
中華街はどこもかしこも
豚まん○○チャンピオンの店とか、
そんなのばかりだった。
それはいまも健在だが、
肝心の中華レストランの影は薄く、
どうも占いの店ばかりが目立ってしょうがない。
皆、そんなに悩み事や相談事があるのか?
などとつぶやきながら雑踏を歩いているうちに、
ふと自分もその気になっていた。
魔が差したというべきか、
呼び込みのオバサンに誘われるまま、
めずらしく暇そうな店の中に入る。
暗い店の奥から
怪しそうな中国人の親爺みたいのが現れる。
結局、この親爺は怪しい日本人だったのだが、
コイツが私の手相を観るなり、
「おっ、社長さんだね」とほざいたので、
第一関門クリアとした。
「社長、これからの4年はイケイケです、
ガンガン行ってくださいよー!」
もうなんだかよく分からないが、
運が乗ってきている時期らしい。
しかし、ホントの事は過ぎてみないと分からないのだ。
で、ウチの奥さんの番。
「なななんと、奥さんの手相、
アイドル線が出ているじゃありませんか!
明日からダンス踊りましょうよ、ダンス!
あのね、このアイドル線がないとね、
AKBには入れないんですよ!
分かります?」
「………」
打って変わり、後ろの席では、
先ほどから暗い話が聞こえてくる。
年輩の奥さまとおぼしき方が、
どうも離婚の相談らしい。
「奥さん、いましかないと思うのよ、
キッパリ別れちゃいなさい!」
「………」
「奥さん、人がいいから…」
(聞こえちゃうんだよなぁ)
だいぶ間があいた。
そして奥さんが力のない声で
「そうしますわ」
「………」
おいおいおい、
そんな大事なことは自分で決めろよと、
思わず後ろを振り返り、
突っ込みを入れようと思ってしまったのだが、
考えてみれば、この人はもうすでに散々思い悩み、
最後に肩をそっと押してもらうように、
この店に足を運んだのかも知れない。
それにしてもスピリチュアルな街だなぁと、感心しきり。
こちらは楽しくストレスの解消も済み、
怪しい占いの店を出ると、
すでに陽が傾いて中華街に長い影が差す。
お土産屋さんで月餅をいくつか買って街を出る。
そして行き交うクルマの波をみながら、
さきほどの街を振り返り、
思わずうーんと唸ってしまった。
いくら占いがブームとはいえ、
割とディープな悩みにも占いはこたえている訳で、
それだけ世の中は複雑・深刻化しているのか、
いや、自ら考えることを放棄しているのか、
最後のひと押しを誰かに求めているのか?
そのあたりの整理がつかない自分がいる。
そもそも自分の行動指針の司令塔は、
己の思考と勘であるハズなのだが、
どうやら世の中には、もっと違う、
何か大きな存在を信じている人達もいる。
歴史を振り返っても、シャーマン、陰陽師、
呪術師、いたこ、祈祷師、霊媒師…
いやいや切りがないなぁ。
思うに、実は私もそんなことを信じる質である。
がしかし、
そこには当然、節操というものがあるなぁ、などと、
アレコレ考えたところで結論が出る訳でもない。
で、相変わらず中華街は元気な訳で、
それにしても思考する、勘を働かせるというのが、
如何に人にとって難しい作業になってしまったのか、
などと思うに至ったのである。
迷える善人の悩みにこたえようとする街、
横浜中華街はいま、人の業が渦巻いている。
きっとあの街は、
イマという時代に生きる人たちの
裏側をあぶり出すにふさわしい、
楽しくも悩ましい解放区なのだろう。