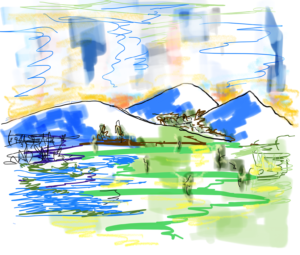半ズボンのポケットのなか
ビー玉がジャラジャラと重くて
手を突っ込んでそのひとつをつまむと
指にひんやりとまあるい感触
強い陽ざしにそのガラスを照らし
屈折が放つ光の不思議に魅せられて
しばらくそれを眺めていた
猛烈にうるさい蝉の音が響き回る境内
水道水をゴクゴク飲んで
頭から水をかぶり
汗だか水だか
びしょびしょのままで
境内のわき道をぬけ
再び竹やぶに分け入る
そんな夏を過ごしていた
陽も傾いて
気がつくと猛烈に腹が減っている
銀ヤンマがスイスイと目の前を横切っても
のっそりと葉の上を歩くカミキリムシにも
もう興味はうせて
空腹のことしか頭にないから
みんなトボトボと歩きだす
道ばたの民家から
魚を焼くけむりとにおい
かまどから立ちのぼる湯気
とたんに家が恋しくなって
疲れた躰で足早に山をくだる
あの頃のぼくらの世界は
たったそれだけだった
きのうあしたは
意識の外のじかんだった
今日という日だけを
精いっぱい生きていた
町内のあの山の向こうはわからない
あの川の先になにがあるのか知らない
僕らの信じられる世界は
たったそれだけで完結していた